ブログ記事を執筆の際に、気をつけたい「著作権」のお話
こんばんは、しろもじです。
今日はブログ記事を作成する上で、知っておくべきこと「著作権」についてお話したいと思います。
とは言え、著作権全てについて語ろうとすると文字数がとんでもない量になりますし、そもそも私も法律の専門家ではありませんので、ここでは概要を述べるだけにしておきます。
ブログの記事を作る上で、最低限このくらいは知っておいた方がいいよ、という程度ですね。
細かいことについては、またおいおいやっていきましょう。
著作権とは?
著作権とよく言われているものには、著作者本人の権利を守る「著作者人格権」と、その著作物を守る「著作権」があります。
著作人格権は、小説を書いている人は小耳に挟んだこともあるかもしれません。
これは「小説をどこで公表するのか」「小説の内容やタイトルを勝手に変えさせない」「著作者の名前を表示する権利」というものですが、小説などを出版される際には、よくこの権利を出版社に委ねるよう契約書に書かれていることがあるんですよね。
これは例えば出版社が、宣伝などをする際に、著作物の一部を抜粋したりすることも、含まれるための措置なのですね。
また、著作物を守る著作権はかなり細かい法律なのですが、簡単に言うと「著作物を勝手に使用されないための法律」と言えるでしょう。
著作物には、小説などの書籍、音楽、映像などはもちろん、今ご覧になっているブログの記事などにも当てはまります。
著作権が適応されるには「世に公表した時点」ではなくって「制作された時点」になります。
まぁこの辺は難しいですよね。判例でも結構割れていたりしますから。
ブログなどの記事で言えば、普通の場合、公開された時点と言って良いと思います。
当然ですが、著作権に守られた著作物を、勝手にコピーや二次配布、改変などを行えば、著作権法違反となってしまいます。
引用とは?
引用とはWikipediaによると、以下のようなものになります。
引用(いんよう、英語:citation, quotation[1])とは、広義には、自己のオリジナル作品のなかで他人の著作を副次的に紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を副次的に自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等[2]のこと。
引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない[3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。
「Wikipedia「引用」より一部抜粋」
わかりましたか?
ちょっと難しいですよね。
すごく簡単に言うと「自分のコンテンツの中に、他のコンテンツを取り入れる必要がある場合、これを引用として、使用することは合法である」ということですね。
上のWikipediaの文章は「引用」になります。
ただし引用には条件があり
- メインのコンテンツの大部分を占めないこと
- 引用先が分かるように明記すること
- 引用であることが明確にされていること
- 勝手に改変しないこと
となっています。
そうは言っても、引用というのは色々なパターンがありますので、次の項で具体的に見ていきましょう。
他のウェブサイトに記載された記事の引用について
まずは、他のウェブサイトに記載された文章の引用についてお話します。
ブログを書いていると、他のウェブサイトの情報を載せたいことがありますよね。
この辺はとても難しい問題なのですが、例えば当サイトの「小説家のためのブログ運営」というカテゴリの記事で、WordPressの設定などについてお話していますよね。
ここで得た知識を、あなたのサイトに書きたいと思ったとします。
その際に、どのようにするのが良いのか、何個かのパターンで見ていきましょう。
「知識を元に、自分で文章や構成を考えて記事化した場合」
これは完全セーフです。
というか、これがアウトになると、世の中のブログはほとんど全てがアウトになりますからね。
「ブログの記事をコピーして、一部を改変して、自分の記事として公開した場合」
これはかなりグレーです。
まずコピーは避けるべきです。
ネットや書籍から得られた知識を元に、自分で書いた文章はオリジナルと言っていいと思いますが、コピーした時点でオリジナルではない要素が入ってしまっています。
「ブログの記事をコピーして、そのまま貼り付けた記事を公開した場合」
完全にアウトです(笑)。
絶対やっちゃダメですよ。
「ブログの記事の一部をコピーして、引用として参照元を明記した上で記事化した場合」
これは引用の要件を守っているので、OKです。
ただし、上に書いたように
- メインのコンテンツの大部分を占めないこと
- 引用先が分かるように明記すること
- 引用であることが明確にされていること
- 勝手に改変しないこと
を守っていないといけません。
最初に私がWikipediaの引用をしているようにすればOKですね。
引用部分が記事の主とならないこと。あくまでも引用は主従の従でないといけません。
比率については難しいところですが、記事全体のうち、多くても1割を超える引用は個人的には良くないと思っています。
また必ずリンクなどを使って、引用元を明らかにしておきましょう。
そして引用であることが明確にされてないといけないので、他のコンテンツとは違うように表記しないといけません。
WordPressなどのHTMLで表記されるものは<blockquote>というタグを使って、引用内容を囲むようにします。
難しそうに聞こえますが、WordPressなら簡単で、引用する文字列を選択してから、メニューから引用ボタンを押せば、上のWikipediaの引用のように表示されるようになります(テーマによって表現は変わります)。
引用ボタンは
これですね。
このことから
「引用元を明確にし、リンクも付けた上で、引用だけで記事を作成した」
「引用元を明確にしたが、記事となじませるように、文中にこっそり引用した」
などは、引用とは言えませんので、やっちゃダメってことになります。
写真の引用について
引用を考える時、ちょっと悩むのが「写真(絵や映像なども含む)を引用してもいいの?」という問題です。
色々なサイトを見て回りましたが、上記の引用ルールを守っていればOKというものも多かったです。
しかし、個人的には写真の引用はちょっと怖いなぁと思います。
前に紹介した「著作権表示フリーの素材サイト」の写真などであれば、安心して使えるかと思いますが、ネットに転がっているものなどは使用しないようが良いと思います。
ちょっと余談になりますが、海外のよく分からないサイトなどの画像も注意した方が良さそうです。
中には「Free」とか表記してあるのに、実際には著作権フリーではなく、後で請求が来るというパターンもあるとか。
確かに世の中には、マンガの画像を載せていたり、アイコンにキャラクターを使っていたりするのをよく見ることもありますが、止めておいたほうが無難です。
またスクリーンショットなどはOKという記載もありました。
私もブログ内でウェブサイトのスクリーンショットを載せたりしていることがありますが、この辺は「好意的な記事なら良いんじゃないかな?」と思っています。
あくまでも引用のルールに則って、というのが条件になりますけどね。
ただし海外の、例えばAmazonさんなんかは、結構うるさいと聞きます。
特にロゴは敏感らしいです。
ロゴを引用するというのは、確かにあまり必要性がなさそうなので、この辺は止めておいたほうがいいでしょう。
音楽の引用について
音楽の引用ってよく意味が分かりませんが(笑)。
音楽はですね、かなり注意しないといけません。
というのも、ご存じの方も多いと思いますが、日本の音楽著作権の多くを仕切っている「JASRAC(日本音楽著作権協会)」という団体は、非常に著作権に敏感です。
今時、サイト上で音楽を鳴らすというのはないと思いますが、動画作成などの際には注意しておきましょうね。
後、歌詞を勝手に載せるのも著作権違反になります。
ごく一部の引用でも不可となる可能性が高いです。気をつけましょう。
Twitterの埋め込みについて
他の方のツイートを自分の記事内に埋め込みたい。
そう思った時、ちょっと迷いますよね。
意外なことに、これは全然OKなのです。
Twitterの規約にはこのように記されています。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して自ら送信、投稿または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(ユーザーの写真および動画もその一部です)の所有権はユーザーにあります。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
ユーザーは、このライセンスには、Twitterが、コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、本サービスを提供、宣伝および向上させるための権利ならびに本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。ユーザーが本サービスを介して送信、投稿、送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、Twitter、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく、当該コンテンツを上記のように追加的に使用できます。
「Twitter利用規約より一部抜粋」
要はTwitterを使い始めた時から、自分のツイートの所有権は自分にあるけど、それをTwitter社や他のユーザーが閲覧したり、使ったりしてもいいよ、ってことですね。
ただし当然ならが条件はあります。
Twitterで提供されている埋め込みコードを使って埋め込むことです。
タイムラインをスクリーンショットして、記事に貼り付けるのは駄目です。
また、自分のコンテンツとして扱うのも駄目です。
キチンと埋め込みして、本人のTwitterへリンクが張られていればOKっていうことですね。
埋め込み方は、簡単です。該当ツイートの右上にある「>が下を向いたマーク」をクリックして「ツイートをサイトに埋め込む」を選ぶとURLが表示されます。
それを、ブログの記事作成画面で「テキストモード(右上にある「ビジュアル」「テキスト」タブの「テキスト」の方)」から貼り付ければOKです。
まぁ、また今度記事にしますね。
まぁそうは言っても、プロフ欄なんかで「転載不可」と書いてある方のは止めておきましょう。
YOUTUBEの埋め込みについて
こちらもTwitter同様に、埋め込みコードを記事に埋め込むだけです。
当然ですが、ダウンロードしたりして、取り込んじゃ駄目ですよ。
また、こちらも「転載不可」などの記載がある場合は、止めておきましょう。
【追記】
音楽関連のPVなどは気をつけましょう。
JASRACさんのサイトに「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用」というページがあります。
簡単に言えば
- 公式PVなら埋め込みOK
- ただし、アフィリエイトなどで収入がある場合はNG
ということです。
確かに「拡散性」を考えると、ブログで埋め込んでもらった方が宣伝にもなるわけですが、商用サイトでの利用はお断りということですね。
この辺りはJASRACさんは、公式回答として「NG」とは言っているものの「個人のサイトを全部駄目と言い切るのは厳しい」ともコメントしています。
難しいところですね……。
止めておいた方が無難でしょう。
YOUTUBEのURLへのリンクならもちろんOKですので、迷ったときはその方法にするべきかもしれません。
それ以前に「ブログ記事にYOUTUBEの埋め込みを貼りまくる」ことや「自分のコンテンツであるかのように振る舞う」ことは、絶対にしてはいけません。
あと、公式でないPVなどは音楽関連以外でも止めておきましょう。
YOUTUBE内にも結構転載動画ってあるんですよね。
他人の動画を転載したもの。
TVなどのコンテンツを許可なく配信しているもの。
これらを埋め込むと、問答無用でNGです。
まとめ
まずお約束ですが「本記事に書かれたことに関して、私は一切の責任を持ちません!」ので、著作権については、ご自身でしっかり調べて運用して下さい。
一応、こう書かないといけませんから、お許し下さい。
著作権っていうのは、なかなか難しいものです。
とは言え、根本的な考え方はシンプルで「他の人のコンテンツを勝手に使わない」ということです。
その中で、法的に認められた引用であればそれを使っていけばいいのです。
ネットというのは、他と繋がってナンボという部分があります。
「引用もさせない」「リンクも張らせない」という考え方は、間違いとは言い切れませんが、あまり有用だとも思えません。
【追記】昨今ではEUのいわゆるリンク税など、少し風向きも変わってきています。現時点で日本の個人サイトにおける環境はさほど変わっていないと思われますが、特に海外文献などは注意が必要になってくるかもしれません。この辺りは、まだまだ不明な点も多いので分かったらまた記事にします。
正しく引用されて、出典へのリンクが張られるのであれば、引用元にとっても実は有利なこともあるんですよね。
それは訪問者が増えることと、SEO的に有利になるということです。
逆に何でも引用、というのも、一時期のキュレーションメディアの問題を見るまでもなく、良くないことです。
少なくても、この記事をご覧のあなたは「他のサイトからコピペした文章を載せたり」「マンガやアニメの画像を勝手に載せたり」はしないようにしましょうね。
今日も最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
それでは、この辺で。また明日!






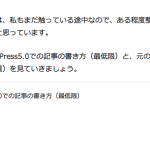






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません