年末年始休みからはじめる小説創作「2020年は小説を書いてみよう」
本記事は「小説を書くのってちょっと興味があるけれど、やったことないしどうやって始めればいいのかもわかんない」という方に向けたものになります。既に小説をゴリゴリ書いている方には「そんなの当たり前じゃん」ってなことも含まれていますのでご了承下さい。
では、本題の「2020年は小説を書いてみよう」という話をしていきます。
逃げ道ではない小説創作

何かを創作すると言えば「絵を描く」「音楽をつくる」「動画をつくる」などがありますが、多くの場合一定のスキルが必要ですよね。イラストにしても漫画にしても作曲にしても、今日始めた人が突然凄いコンテンツを作れるという可能性は、ほぼ0だと思われます。
よくあるのが「絵が描けないから小説を書く」という、逃げ道的な理由で小説執筆に行き着くというもの。よくWebでも「絵が描けなくてもOK」と原作コンテストなども行われたりしていますし。でも実際に小説を書いてみると分かるんですが、案外奥が深いのが小説執筆なんですよね。
奥が深いというのは「文法を理解するのが大変」ということではなく「面白い話を文章でつくる」という難しさがあるという意味です。すごく失礼なことを言えば、例えば漫画なんかだと平凡なストーリーでも、登場人物が可愛かったりかっこよかったりするだけで、それなりに読めたりします。
でも小説では「文字」という表現方法しかないため、他の要素でカバーすることはできません。つまりある程度話が面白くないと、小説というのは評価されにくいということですね。
そういう意味で、私は「小説は漫画の下位互換でない」と思っています。小説には小説の、漫画には漫画の、音楽には音楽の、動画には動画の難しさやノウハウがあり、それぞれの特徴や表現方法があるので、違ったものだということが言えるのではないでしょうか。
まぁ「絵が描けないから小説を書く」という動機がいけないというわけでもないとは思います。ただ「絵よりは簡単なんだろ」で始めてしまうと、あとで「あれれ?」ということになるかもしれないというわけですね。
小説って難しいんかい
冒頭からいきなりハードルを上げるような話をしてしまったので「小説書くのって難しいのか」と諦めかけた方もいらっしゃるかもしれません。
でもご安心下さい。小説は決して難しいわけではありません。あくまでも「薄っぺらで何も考えなくてもできちゃうわけじゃない」というだけの話なんですよ。例えばキャッチボールって楽しいじゃないですか。極端な話、グロープとか用意しなくてもこんにゃくボール(正式名称が分からないんですけど、ぷにょぷにょの柔らかいボールのこと)を投げあってるだけでも、結構楽しめますよね?

しかしだからと言って、キャッチボールが底の浅いものというわけでもないですよね。慣れてくると速いスピードで投げ合ったり、高いボールを投げたり、背面キャッチをしてみたり、もっと言えば投げて打ってみたり野球の試合をしてみたり……というように、やればやるほど難しさは増していきますし面白さも増えていきます。
小説執筆も似たようなもので「簡単に書くこともできるけど、もっと複雑な話をつくることもできる」という感じで、色々な段階やバリエーションがあるということです。
ちょっと勘違いしてしまいそうなのですが、小難しい単語を使った小説や複雑なトリックや伏線を用いた小説の方が優れていて、そうじゃないものよりも高尚だというわけではありません。
先程の例で言えば「こんにゃくボールを投げ合ってるのが楽しいよね」という楽しみ方もあるわけで、人それぞれの創作ができるという意味です。
もう少し具体的な話をしてみましょう。
文法はとりあえず後回しで
小説を書き始めたときに、最初にぶつかる壁のひとつに「文章が単調になってしまう」というものがあります。ものすごく極端な例を書いてみます。
「今年のクリスマスはなにしてたの?」とAは言った。
「クリスマス? なにそれおいしいの?」とBは答えた。
「いやケーキは美味しいけど、クリスマスは食べ物じゃないよ」とAは言った。
「クリスマスケーキ……彼女と一緒に食べたかったなぁ……」とBは言った。
「でもお前、彼女いないじゃん」とAは言った。
こんな感じの文章が続くと、流石に少し単調に思えてしまいますよね。
でも実はこれとても簡単に解決する方法があるんです。それは最初に「AはBに聞いた」と付けて、後は全部省略しちゃう方法です。やってみましょう。
「今年のクリスマスはなにしてたの?」とAはBに聞いた。
「クリスマス? なにそれおいしいの?」
「いやケーキは美味しいけど、クリスマスは食べ物じゃないよ」
「クリスマスケーキ……彼女と一緒に食べたかったなぁ……」
「でもお前、彼女いないじゃん」
多少すっきりしましたよね?
このように会話劇にすると、かなり書きやすくなりますしまた最近では読みやすく思う人も多いようです。
小説は上のように「会話文」と「地の文」で成り立っていて、地の文とは会話文以外を指し示します。「会話文を書くのは困らないけど、地の文を書くのは難しい」と思う人が多いのではないでしょうか?
それは会話文は普段行っている会話をベースにして書けるのですが、地の文って本を読んだり文章に慣れていないとなかなか思いつかないからですね。でも、上に挙げたように会話文中心の小説だって、ちゃんとした小説だと私は思います。
また地の文にしても「こうしなければならない」というものはない、と私は思っています。
「こうする方がいいかも」というのはあるとは思いますが「こうしないと間違いである」というのは、それほど深く考えなくてもいいと思います。
第一、それを言い出したら、現代日本語はほとんど間違っていることになってしまいますからね。
その上で「もう少し地の文を上手く書けるようになりたいなぁ」と思えば、他の小説をたくさん読んでみたり、文章の本を買ってみたりすればいいのではないでしょうか?
まずは1作書いてみる
一番大切なことは「まず1作を書いてみる」ということだと思います。
上で触れたように「小説を書くのは漫画とかに比べて簡単だろ」と思っている方でも、最初の1作をいざ書き始めると「あれ、あれれ」となると思います。
「なんか思ってたのと違う」
「こういうときどう書けばいいのか分からない」
「どう表現するのがいいの?」
「キャラクタの会話が不自然」
「ストーリーが思いつかない」
など、色々な問題が出てくるはずです(もし何も出てこず、思っていた以上によくできた方はきっと天才なので、すぐに公募やコンテストに応募してみましょう)。
途中で投げ出したくなるかもしれません。次に行きたくなることもあるでしょう。
でもおすすめは「一度最後まで書いてみる」ということです。
最初から思い通りにならないのは当たり前です。むしろ思い通りにならないからこそ、面白いと言えるわけです。誰に迷惑をかけるものでもないので、気にする必要もありません。
最後まで書いてみて「あー!」と思ったところは次に直せばいいだけです。自分は毎回「ああああー!」と思っていますが、それでも「次はもっとよくなるはず」と思いながら書いています。
世の中のほとんどのものは「やった回数だけ上手くなる」ようにできています。40歳過ぎてバイクの免許を取りに行ったとき、最初は絶望しかなかったんですが、それでも数時間も乗ればある程度上手く乗ることができるようになります。
それと同じように文章を書くというのも、やればやるほど上手くなっていくものだと思っています。もちろん「書く」だけじゃなく「読む」も大切な要素なので、色々な文章を読むのがいいと思います。個人的には「好きな小説だけ読む」のではなく、それ以外の文章にもできるだけ目を通すのが良いのではないかなぁと思っています。
メインは好きなもの、書きたいものを読むべきですが、それだけだと分からないことも多いですからね。
創作は自由
上述しましたが、小説執筆において「こうしなければならない」ということは、ほとんどありません。公募などに出す場合には書式などがありますからそれには合致させないとダメですけど、それ以外でそれほど厳格なルールはありません。
ただ「読む人が不快になるもの」は避けた方がいいのかもしれませんけどね。よく言われるのが句読点の使い方や三点リーダーなどの使用でしょうか。その辺りは次の記事で少しだけ触れています。
ビジネス文章や公文書などはある程度のルールがありますけど、小説は基本的に自由だと思います。地の文が「小学生の日記並の文章」でも面白い小説はありますし、ものすごくテクニックを駆使して技工をふんだんい使った面白くない小説もあります。もちろん逆もあります。
ですので最初は「小説執筆のテクニック集」とか「文章上達スキルアップ」みたいな本は、とりあえず本棚にしまっておきましょう。そういうのは必要になったときに読めばいいだけです。
確かに誤字や文法の基本に沿ってない文書は、読み手の混乱を招くので避けた方がいいですけど、それすらもWebの時代であれば「後から修正」ということが簡単にできるので、最初は深く考える必要はありません。
誰がための小説執筆
最後にひとつだけ。
「なんのために小説を書くのか?」だけははっきりさせておくといいかもしれません。
小説に限らず創作というのは「誰かに見てもらって評価される」ためにあります。なので、多くの場合は書いた小説が「Web小説投稿サイトで高評価を得る」ことや「コンテストや公募で賞を獲る」ことが目的になります。
これは間違っているわけではないのですが、ぜひそれ以外にもうひとつ柱を立ててみて下さい。私の場合は「自分が考えた話が、文字として再現される」という喜びを持っています。うまく言えないのですが「頭の中で考えているストーリー」というのが結構あって、それを具体的に文字として起こすことが楽しいと感じるんですよね。
そういうのがあると「人に評価されない」ときでも、創作を止めることがなくなります。
これは前にも書いたことがあります。
人の評価は人の評価です。私たちは物心ついたときから「人の評価」によって人生を左右されて生きています。学校では先生の、家では家族の、地域では近所の方の、会社では上司の評価が私たちにとって重要な要素となっています。
でもそれは創作というカテゴリでは、ときとして邪魔になることもあります。
もちろん、コメントを頂いた方の話や、具体的なPVや評価の数など、そういうのを考えて書くというのも大切なことかもしれません。でもそれだけが創作のモチベーションになってしまうと、評価されないときに「俺、なにやってんだろ」ということになってしまい、最終的に「やーめた」となってしまいます。
もしそれで別の楽しいことを見つけて、人生楽しく生きられるのであればそれもいいのですが、もし「創作を諦めたこと」がずっと心に刺さったトゲのようになってしまうのでは、ちょっと悲しいことになってしまいます。
どんなことでもそうなのですが「モチベーションは自分の中に持つ」ことが大切です。そうすることで他の要素に左右されず、長く続けていくことができると思います。
まとめ
凄く長い文章になってしまいました。最後までお読み頂いた方、ありがとうございます。
若干(かなり?)まとまりがない文章になってしまいましたが、ひとりでも「書いてみるか」と思って下さる方がいれば幸いです。
蛇足になりますが、私の経験からいくつかだけ。
「最初の小説は超大作にしない方がいい」という話はよく聞きますが、私は別にどっちでもいいと思います。「設定などに凝りすぎて、いつまで経っても本編を書けない」というのはちょっと困ってしまいますけど「色々盛りすぎて収集がつかなくなる」というのは、結構よくあることです(しみじみ)。
なので、その辺りはそれほど気にしないで大丈夫だと思います。盛って盛ってモリモリ盛って、どうにもならなくなったら次から気をつければいいだけ。
そのくらいの気楽さでやればいいでしょう。
またWeb投稿サイトが増えた結果、小説を応募することの敷居は随分下がってきていると思われます。また出版不況ですが、出版点数はそれほど減ってない(少し前のデータではむしろ増えている)ので、それはつまり「作者が増えている」ということになります。
作者が増えるということは「一攫千金」というのはなくなっていると思った方がいいでしょう。前にも言いましたが、最近だとラノベ系の初版発行部数は1万部未満が一般的なのだそう。
定価1200円の本として印税が8%だとすると1万部発行でも100万円にもなりません。それでも2巻、3巻と発行されたり、次作も約束されているのならばいいのですが、作者は掃いて捨てるほどいるわけですからそういうチャンスは限りなく少なくなります。
なので「小説書いて一発当ててやるぜ」というのは、最早都市伝説レベルの話だと思います(0ではないですが)。上にも書きましたが、そういうところもモチベーションを持っていくべきではないでしょうね。
繰り返しになりますが、創作は自由です。あまり気負わず、楽しめる創作ライフを送れますように。





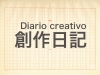






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません