コミケは東京モーターショーの轍を踏むのか? 8月16日より台湾で「漫博18」が開催
こんにちは、しろもじです。
ネットをウロウロしていたら「台湾で8月16日より『2018漫画博覧会(漫博18)』が開催される」という記事を見ました。
(Record China)
リンク先の記事を見ると分かるのですが、漫画やアニメ、ライトノベルを中心とした博覧会で、1995年から一部の例外を除き、毎年開催されているとなっています。
また、日本の漫画、アニメにも言及されており、現地でも大変人気を博している、ということで、思わず嬉しくなったりもしてきます。
しかし一方で、気になる記述も。
2017年は8月10~14日の開催で、来場者は52万1000人だった。
Record Chinaより引用
これ、多少の誤差はあるもののコミケとほぼ同じ規模。
コミケが夏・冬の2回開催と考えると、半分の規模と見ることもできますし、そもそも「同人誌即売会」としての色が強いコミケに対し、漫博は企業出展がベースということで、安易に比較はできませんが、台湾の人口を考慮すると、結構な来場者数だと思いました。
東京モーターショーの轍?
このニュースを見てて、フッと脳裏を過ったのが「東京モーターショー」。
自動車のショーですね。
フランクフルト、パリ、ジュネーブ、北米と並び「世界5大モーターショー」ともてはやされた「東京モーターショー」。
今でも「5大モーターショーである」と言えるのかもしれませんが、規模的に言えば「上海モーターショー」に完全に上回れ、徐々に存在感を失いつつあります。
現に、世界のメーカーが初公開(ワールドプレミア)するのも、東京よりも上海の方が多くなっているとか。
自動車と言えば、日本では大きなメーカーだけでもトヨタ・ホンダ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツなど数多く有しており、世界的に見ても「自動車大国」と言って間違いない存在感を見せています。
もちろん、中国の自動車メーカーも多数誕生しており、そういう部分が上海モーターショーの躍進に関わっている、とも言えます。
また、日本のモータリゼーションは成熟期に入っており、発展期の中国と熱量が違うのも分かります。
しかしそれでも、自動車大国のモーターショーが、どうして規模も質も劣っているはずの国のモーターショーより劣ってしまったのでしょうか?
一番には「人口が違う」というのがあると思われます。
13億人ですからね。あちらは。
日本比で13倍です。
無論「自動車を買える人口」というのはイコールではありませんから、一概には比べられませんが、それでも富裕層の数、将来の発展余地などを考えると、どうしても中国には勝てません。
例え、日本のメーカーと言えども、商売をやっているわけですから「規模が大きく、購買力の高い地域での販促活動」には力を入れることになります。
上のリンク先の記事にもありますが「台湾角川」など、日本メーカーも既に進出を始めています。
いずれ、出版社の主戦場は日本ではなく、海外(特にアジア地域)に移っていくのでしょう。
それは仕方がないことだと思います。
さて、ここでひとつ疑問が浮かび上がります。
「何が問題なんだ? 良いことじゃないか」
そう思いませんか?
日本で作られた、小説、ライトノベル、漫画、アニメは翻訳して海外で売られることになります。
日本という市場は、これからドンドン縮小していきます。
恐らく、単価の安い仕事はあっという間になくなるか、自動化されるか、海外に移転されます(今でも行われていますが)。
創作物も同様でしょう。
ふたつ懸念があります。
ひとつは「創作の場が、やがて海外へと移転していくこと」。
もうひとつは「創作の対象が海外に向かうことにより、より現地ニーズに合ったものに変異していくこと」。
1つ目の懸念は、もはや我々創作者が考えても仕方がないことなのかもしれません。
自動車に比べて、輸出が簡単な創作物でも「現地のレベルが上がってくれば、そこで創られる」ようになるのは必然です。
特にアニメータの過酷な現状は、何度も報道されたりしていますから、これらの改善策として「アニメータの待遇改善」よりは「海外のアニメータを使う」ということになるのは、経営判断としては間違っていないではないでしょうか?
私が心配しているのは2つ目。
自動車も、元々は国内用に設計・生産されたものを、現地の法規に合わせて輸出していました。
それが段々、現地生産するようになったり、海外の方が市場が大きいので、設計段階で海外の要望を反映するようになって、日本車の個性は失われていきました。
昔、一時期話題になったのですが、アメリカなどの若者の間で「シビック」「シルビア」「GT-R」などの日本車が人気を博していた時代がありました。
今はどうなっているのはよく分かりませんが、YOUTUBEなどで検索してみると、ちょっと前の動画ばかりが出てくるので、下火になってきているのではないかと推察できます。
また、日本市場においても、そのような「海外のニーズを反映した車」が氾濫することになり、一部のメーカーでは主力車種でさえ、日本のニーズよりも海外ニーズを優先させて開発を行った結果、大きく魅力を落としてしまいました。
日本メーカーの幹部が「若者のクルマ離れ」とよく言っていますが、これは「若者の収入が上がらないこと」と同時に「日本の若者が欲しくなるような車を開発してこなかったメーカーの責任」があると、私は思っています。
どちらにしても、若者のせいじゃなく、大人のせいなのですよね。
「売れるから」「儲かるから」と目先の利益に振り回されて、中長期的なブランドというものを考えてこなかったメーカーの責任は重いと思います。
創作物も、その轍を踏むのではないか?
今はまだ「国内で創ったものを翻訳して輸出している」だけですが、今後「海外のニーズを踏まえた作品を海外で創り、それを国内に持ってくる」そういう時代がやってくるのではないか?
その時、国内の消費者はそれを受け入れることができるのだろうか?
もっと恐ろしいのが「それならそもそも日本というタグが付いた商品じゃなくて、いいんじゃない」と世界から思われるのではないか?
そういうことを、考えていたわけですね。
お盆だし、暇だし(笑)。
まぁ、あくまでも個人の一意見なので、あまり真に受けないで「へぇ」と思って頂けるとありがたいです。
ひとつだけ、救いようがあると言えば、まさにコミケの世界の話で。
自動車は個人では作れません。
1台くらいなら、何年かかければ作れるかもしれませんが、量産はできません。
ところが、創作物はそうではありません。
個人が創って、個人が量産できます。
個人がメーカーと言っても良いと思います。
ですので、現時点で「メーカーである」と思っている出版社が、万が一間違った方向にいっても、個人である我々メーカーが生き残る道はあるのではないかと思っています。
やや、突飛な話になってしまいましたが、今回はこの辺で。
あ、決して台湾の「漫博18」がいけないとか、そういうディスっている記事ではありませんからね。蛇足ながら。






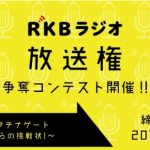
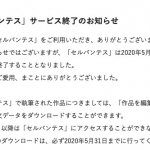


ディスカッション
コメント一覧
それ書きたい! でもすっごく難しそう。ちょっと私には手に負えないかも。SFって、ものすごく勉強しないと書けませんよね。もちろんそれが楽しいんですけど。しろもじさんがその設定をどう料理するのか、見てみたいです。でも、もちろん書きたいもの優先で!
『さよなら』の第2章、実はぜんぜん自信がないんです。光景浮かびました? よかった。私もその場面の空気感を伝えるのってすごく重要だと思ってます。それがないと読んでる人に情報が入っていかないんじゃないかなーと。ハードル……上がりましたけど、が、がんばります!
>しろもじさんがその設定をどう料理するのか
ハードルを上げたつもりが、自分に跳ね返ってしまっています(笑)。
そんな大層なものにはならないと思いますが。
光景、ちゃんと浮かびましたよ。もしかしたら、それは作者(Han Luさん)の思っているのは違うかもしれませんが、それでも読んでいる側の頭の中に浮かんでくる文章と、そうでない文章ってありますからね。なかなか勉強になるところです。
Han Luです。こんばんはー。
漫博、知りませんでした。でも、台湾に限らずいろんな国で漫画やアニメの展示会やってますよね。日本の文化の特殊性ってすごいなーといつも思います。
実は、今回しろもじさんが後半に書いてること、私も同じようなことを考えてました。
>今はまだ「国内で創ったものを翻訳して輸出している」だけですが、今後「海外のニーズを踏まえた作品を海外で創り、それを国内に持ってくる」そういう時代がやってくるのではないか?
私はそういうことが起こる可能性もあるんじゃないかと思ってます。
>その時、国内の消費者はそれを受け入れることができるのだろうか?
>もっと恐ろしいのが「それならそもそも日本というタグが付いた商品じゃなくて、いいんじゃない」と世界から思われるのではないか?
たぶん日本の消費者は受け入れないですよね。そして、もし海外のニーズが一般化して、創作物にグローバルスタンダードみたいなものができたら、日本は創作物でもガラパゴス化しちゃうんじゃないか、ということですよね。
難しいです。私はその可能性を否定することはできないんじゃないかと思います。でも一方で、創作物は車や携帯電話のような耐久消費財ではないですから。冒頭に言った日本文化の特殊性がどこまで通用するのか、ということもあるかなーと。
実は、このあたりのことは、今私がカクヨムに投稿している『さよなら、ライトノベル』の内容とすごくシンクロしているんですよ。といいますか、非常に重要な部分に関わってくるテーマなのです。もしかしたら、しろもじさんにはラストが予測できちゃうかも。
私自身まだもやもやとしていたところでしたので、考えを整理できて助かりました。すごく嬉しいタイミングでした。なにせプロット立ててないので。ありがとうございました!
Han Luさん、おはようございます。コメントありがとうございます。
漫博は私も知らなかったんですよね。Han Luさんの仰る通り、確かに海外ではそういうのが行われているのはボヤッとは知っていたのですが(フランスとかが有名?)。
>たぶん日本の消費者は受け入れないですよね。
これは、私も同意です。どういう構造になっているのか分からないのですが、以前アニメを観ていて「なんか変なアニメだな」と思っていたら、エンディングのスタッフロールに、ずらっと大陸系のお名前が。
これは「あちらの創った作品など駄目だ」と否定しているわけではなく「やっぱりちょっとだけ感性が違うのかな?」ということです。
まぁ、日本の方が創られたものでも同じように思ったりすることはあるんですけど(笑)。
しかし、軸足がそちらに傾いてしまうと「ちょっと違うな」というものが溢れるようになるんじゃないかと思っています。
そして、そのうちそちらの方がスタンダードになっていくんじゃないかと。
>創作物は車や携帯電話のような耐久消費財ではない
そうですね。確かにその通りです。そこは長くなりそうなので端折ったところなのですが、私が書こうとしていたのは「娯楽物だからこそ、サイクルも早く、安価であり、比較できないのかもしれない」ということでした。
仰られているような考えはなかなか面白いですね。
私もですね、実はそれに関連したことの小説のプロットを創っていたりします。
日本の創作物は確かに日本人向けに創られたもので、海外で同じ比率で受け入れられる可能性は少ない。が、とは言え、少なからずシンクロしてしまう人たちもいる。
現在の国家とは別のコミュニティがあってもいいのかも。今はネットという便利なものがあるのだから。
更に、国家自体が将来的に「それぞれ独自の文化考え方を持った共同体」となっていくのならば、その間を自由に移動できるようになり、市民は消費者と変わっていくのではないか。
しかし、そうなったとき、多様性は失われてしまうことになるので……みたいな。
何言ってるのか分からなくなりました(笑)。
まー、創作者としては、国内のそれも一部のユーザだけを見ていては、駄目だよなぁということでしょうか。
あ、最後の部分。
『さよなら、ライトノベル』もそういう展開なんですね。
なるほど。ラスト…ラスト……。センセー、分かりません(笑)。
こちらこそ、こういう記事にコメント頂けると、考えの整理や新しい見方などが分かったりして、面白いです。
ありがとうございます!
お返事ありがとうございます。
>現在の国家とは別のコミュニティがあってもいいのかも。今はネットという便利なものがあるのだから。
更に、国家自体が将来的に「それぞれ独自の文化考え方を持った共同体」となっていくのならば、その間を自由に移動できるようになり、市民は消費者と変わっていくのではないか。
しかし、そうなったとき、多様性は失われてしまうことになるので……みたいな。
これ、すっごく面白いです! 確かに、これだけで一本書けそうなネタですね。ぜひ書いてください
! 読みたい! それで、ハヤカワのSFコンテストに応募しましょう! マジで!
たぶん、いろんな種類の共同体が出てきますよね。あと、創作物だけじゃなくて、いろんなレイヤー、例えばスポーツとかが出てきて、個人は複数のレイヤーにまたがって参加したり。多様性は……その共同体がどこまでカバーするかの範囲によりますよね。それにしても、しろもじさんって、面白いこと考えますよねー。
『さよなら、ライトノベル』のラストは実はハッキリとは固まっていません。でも、なんとなーくのイメージがしろもじさんのブログで補強された気がします。今日からまた投稿再開すると思います。いつも応援ありがとうございます!
こちらこそ、お返事ありがとうございます。
面白そうですか?
21世紀中盤以降のSFものなのですが、VR(ヘッドセットではなく、スター・トレックのホロデッキのようなもの)を主軸として、AIが管理する国家、人間が管理する国家などがあり、その中で「国家がコミュニティとなっていき、それぞれ独自の法律、文化を持ち、人間は所属する国家・コミュニティを選択できるようになる」という話なんですよね。
ただ、すごく複雑で、SFの設定をどの程度リアリティのあるものにするのかで悩んだりしています。
その手の本を読んだりして勉強しているのですが、なかなか……。
良かったら、Han Luさん書きませんか?
早いもの勝ちですよ(笑)。
まぁ、今の小説が一段落(終わらなくても)したら、書……きたいかなぁ、とは思っています。
別に書きたい話もあるので、どちらになるか分からないのですが。
『さよなら、ライトノベル』再開ですか!
前にも言ったのですが、あの空気感というか、雰囲気というか、とても好きなんですよね。
1章も良かったけど、個人的には2章が良い。
最近「キャラクターの面白さやストーリー展開も大切だけど、文章でその場の空気を伝えるのはとても大切で、とても大変だ」ということを思っています。
自分の脳内と読者の脳内が、必ずしもリンクしている必要はないと思うんですけど、キチンと伝えられる部分を伝えるというのは必要かと。
それが『さよなら、ライトノベル』の場合、1章は日本の光景なので、ある程度想像できるとしても、2章の海外の光景があれほど脳裏に浮かんでくるのは何でだろう……?
とか考えていました。
そういうわけで、楽しみにしております。もしかしたらハードルを上げてしまったかも(笑)