NHKがネット同時配信をスタート 将来的な課金制度への足がかり?
昨日2020年3月1日より、NHKが満を持してのネット同時配信「NHKプラス」を開始しました。
ネットを中心に「将来的にネット利用者からも受信料を取るのではないか?」と懸念されていますよね。あくまでも個人的な意見ですが、私は間違いなくそれを見越していると思っています。
※ちなみに本記事はNHKを糾弾するものではありません。あくまでも色々なデータを見て、状況を整理し未来を予想する記事になります。
NHKプラスとは?

冒頭で書いたように、地上波などがネットで同時配信されるサービスです。
受信契約者とその家族(同一生計者)は追加料金なしで視聴でき、Webブラウザ、スマホアプリ(Android、iOS)で利用できます。
利用においてはIDが必要で、未登録だと画面にテロップで注意喚起が表示されます(でも視聴はできるみたい)。
全てのNHKチャンネルが視聴できるわけではなく、現時点では「NHK総合」「Eテレ」に限られているようです。
試しにWebブラウザから視聴する方は、上のリンク先から「NHKプラスはこちら」をクリックすると、視聴画面に行くことができます(IDなどは「ログイン」からするみたい)。
未ログイン状態で観てみたのですが、画質もいいしストリーミングも安定しています。
NHK受信料は高いの?
きちんと視聴するには、上に書いたようにログインが必要です。
登録には
- メールアドレスを入力
- 送られてきたメールからWebにアクセスし、必要事項を入力
- 1〜3週間ほどでNHKからハガキが送られてくるので、書かれている確認コードを入力
という手順が必要。ちょっとややこしいですけど、住所確認の意味合いがあるのでしょう。
というわけで、NHKとの契約が必要なわけですが、そもそもNHKの受信料は高いのでしょうか?
あんまり気にしたことがないので改めて調べてみると、口座振替・月払いで1,260円。BS込みだと2,230円です。
一概に比べられないのですけど、
| (VOD)サービス | 月額 |
| Netflix(スタンダード) | 1,320円 |
| Amazon Prime | 500円 |
| dアニメストア | 440円 |
| 英BBS | 1,673円 |
※価格は税込み。TEXT FIELD調べ。間違いがあった場合はご容赦下さい。
※BBCの価格については、年額145.5ポンドを元に円ポンド138円として計算し月額換算
と言う感じで、うーんやっぱりちょっと高いような……。
もちろん収益モデルが違うので、同じ土俵に置くのは乱暴かもしれません。けど、支払う方にしてみれば「視聴の対価」という観点では同じことですからね。
個人的には地上波だけでdアニメストアの3倍というのは、ちょっとボリすぎです。
どうしてこんなに高いのか?
プライムビデオやNetflixとは違い、NHKは基本的に「受信設備を持っている者は支払い義務がある」とされています。
つまり「見てない」が通用しないんですよね。
ということは、契約世帯も上のサービスと比べると段違いに多いはず。普通、サービス利用者が多いサービスは、利用料金が下がる傾向にあります。
ただしそれは「競争相手がいる場合」で、NHKのような独占している団体には当てはまりません。Amazonだってdアニメだって、ライバルがいっぱいいるから低価格にしているわけです。もし世の中にAmazonプライムビデオしかなかったら、あんなに安い料金にはしておかないですよね。
だから高い理由の一つが「競争原理が働いていない」ということになります。
また競争が働いていないということは、少し乱暴な言い方をすれば「今入ってきているものを無理に下げることをしないで、使う方向にすればいい」ということになりがちです。
少し調べてみたんですけど、30年度末で「建設積立資産」という名目で1,707億円、「財政安定のための繰越金」という名目で1,061億円もの積立資産があるんですよ。
※PDFです。5P参照
建設積立資産とは放送センターの建て替えのためのお金ですね。
基本的にはセンター建て替えについてはいいんじゃないかな、とは思っています。建設費は民間に流れるわけですから、言い換えれば経済の循環につながるからです。
でも積立金、お前はダメだ。
2,700億近くのお金がNHKで止まっているわけですよ。それの原資は当然受信料です。しかも余剰金がありながら、交付金までもらっているというのはどういうことでしょうか?
それと散々言われている人件費。
NHKは「優秀な人材確保のためには、一定の報酬が必要」と言っていますが、公共放送とは最低限で運営されるべきものではないでしょうか?
ですが実態は違っていて、NHKの会長の年俸はなんと3,092万円ですよ。
総理大臣の年俸(と言っていいのか分かりませんが)はおおよそ4,000万から5,000万程度と言われていますし、日銀総裁でも3,500万くらいらしい(TEXT FIELD調べ)。
もちろん会長だけに留まらず、副会長2,690万円、専務理事2,360万円、理事2,206万円と、なかなか景気のよい数字が並んでいます。
一般職員の給与は公開されてないようですけど、30年度予算で給与が1,164.4億円、要員数が10,318人ですから、ざっくり割ると……1,128万円……計算合ってる?(笑)
ま、TBSが1,600万くらいらしいので、そう考えるとお安いの……かも?
でも繰り返しになりますが、選択権がなく強制的に徴収されるわけですから、そこを民間並というのはちょっとおかしいと思うんですけどねぇ。
結局は上で書いたように「入ってくるものを無理に減らさずに、できるだけ現状を維持する」という施策が取られていて、そのせいで受信料が下がらないということになっているんだと思うんですよね。
ただこれはNHKが悪いというよりも、NHKに所属している人からすれば当たり前の感覚なのかもしれません。
だって私たちだって「自分の給料を減らしてもいいから、売っている商品の価格を下げて下さい」とは言わないですからね。
つまり自浄作用がないのは当たり前、というわけです。ですから、NHKの外からの改革が必要になってくるってわけですね。
ネットからの受信料徴収はある?
さて、今回のNHKプラスでは、NHKは「NHKプラスで別途料金は取らないし、その予定もない」と言っています。でも、冒頭でお話したようにそんなわけがない、と私は思っています。
ネット同時配信の裏には「ネット配信による予算確保」の意味合いもあると思いますが、将来的なことを考えればTVというメディアは今後ますます衰退していくことが予想されます。
総務省が発行している「情報通信白書」の30年度版に、面白いデータが載っていました。
※PDFで開きます
世代別の2013年から2017年のテレビ、ネット、新聞、ラジオの視聴時間の推移のグラフがあります。
これによると10代のテレビ(リアルタイム視聴)の時間は2013年には102分だったのに対し、2017年では73分と30分近く減っています。
同じように20代では-36分、30代は-36分、40代は+7分、50代は+26分、60代は-5分と、若い世代を中心にテレビの視聴時間は減ってきています。
ちなみに私は現在ほとんどテレビは観ていません。
大きなニュースがあったときとか、実家に立ち寄ったときに家族が観ているものを一緒に観る程度です。
正直「まだこんなに観てるんだ」と驚いた数字だったのですが、この傾向は今後ますます顕著になっていきそうです。
恐らく「TV持ってない」という世帯も出てくるのではないでしょうか?
というか、TVerがあればたいていの番組は観られますし、YoutubeにVODにと観るものはたくさんありすぎる時代です。わざわざ高いTVを買って、月額課金(NHK受信料)を払う必要性を感じない人は、もっと増えてくるでしょう。
そうなると困るのがNHKです。
NHK受信料の徴収の前提は「受信設備を所有していること」です。つまりTVを持っていないと、徴収できないというわけですね。
一時期ワンセグからも受信料を徴収するということが話題になりましたが、ワンセグ自体が終わってしまっているので、スマホから受信料を取る手段がなくなってしまいました。
というわけで、ネット配信というわけですね。
そういうことを考えると「今後NHKがネット配信の受信料を徴収しない」というのが、あり得ない話だと私は思うんですよね。
これからの公共放送とは?
先月中頃に、英BBCが受信料制度を廃止し視聴した分だけ課金する方式へ移行することを検討していると報道されていました。
BBCがどうなるのかは私には分かりませんが、こういう議論が出てくるということ自体、よいことだと思われます(色々な思惑はあるんでしょうけど)。
日本では国会で取り上げられたというニュースはほとんど見ませんからね(一部議員さんが質問していたのがYoutubeに上がっていましたけど)。
前述したように「その組織内の人間が、自分たちの身を切るような改革はできない」わけですから、NHKを改革するのであれば外部組織、つまりは政府関係からの圧力が必要というわけです。
現在NHKは
- NHK総合テレビジョン
- NHK Eテレ
- NHK BS1
- NHK BSプレミアム
- NHK BS 4K
- NHK BS 8K
という6チャンネルを持っています(他にラジオも3波)。
正直こんなに要りません。先程も言いましたが、公共放送は最低限でいいはずです。
国内地上波1、BS1、海外チャンネル1,ラジオ1くらいで十分なのではないでしょうか?
ネットで散々言われている「スクランブル化」は、絶対にあり得ないでしょう。スクランブル化したら、受信料が大幅に下がっちゃいますからね。
受信料が下がれば今度は税金で補填されるようになります。なので、やるとしたらまず「NHKのスリム化」から始めるべきでしょう。
もちろん「じゃ、明日から」というわけにはいきません。職員さんがいくら高給であったとしても、いきなり首にはできませんから。
世代が変わるくらいの年月は必要になってくるのではないでしょうか?
もしくは郵政のように完全民営化するか、ですかね。
ややNHK批判の記事になってしまいましたが、NHKも素晴らしい番組をいくつもつくっています。民法はバラエティばかりになってしまった(ニュースさえバラエティ化してる)中、NHKのドキュメンタリなんかは、なかなか見応えがあって私は好きです(一時期、プロフェッショナルとかプライムビデオにあったんですけどねぇ)。
個人的には民営化などではなく、公共放送としての正しい立ち位置を確保して欲しいな、と切に願っています。




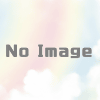


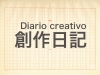



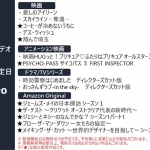




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません