アウトプットは誰のものなのか?
こんばんは、しろもじです。
「インプットとアウトプット」と聞くと、作家の方々は「インプット=情報を仕入れる」「アウトプット=創作する」というイメージが湧くと思います。
今回の話はそこから少し枠を広げて、生きていく中で自分の中に入ってくるもの全てと、出て行くもの全てについてになります。
アウトプットは自分次第
以前このような記事を書きました。
これは「批判的なコメント」というインプットに対する「対処方法」というアウトプットのお話でした。
この記事を書いていて思ったのですが、インプットに対する反応(アウトプット)は、自分でコントロールが可能なんですよね。
インプットは変えることができないけれど、アウトプットは自分で変えることができる。
つまり、どういうアクションを起こすかは自分次第ということ。
批判的なコメントだけではなく、好意的なコメントだって同じことが言えるでしょう。
コメントに限らず、読んだ本、観た映画、聞いた話、なんでもそうですよね。
最近は昔に比べるとインプットする(される)量が格段に増えてきました。
入ってくるものを整理する暇も時間もないということもあるかもしれません。
それでもアウトプットする時は、自分が選択することができることだけは確かです。
そうは言っても人間だもの
でも、頭では分かっていても、なかなかそう上手くはいかないんだよ。
そう思われる方も多いでしょう。
私もそうです。
思うに、これは学校教育の問題じゃないかと思うんですよね。
学校では教えられること(インプット)に対して、正しい答えを出すこと(アウトプット)が求められます。
つまり、自分がどう思ったのかは関係なく、正解を導き出すことが正しいとされるわけですね。
このこと自体は、一概に駄目だとは言えないんですよね。
1+1が「僕は10だと思います」では、困ることもあるからです。
だから、本当はそういう教育と、考える教育を同時で教えるべきだと思うんですよね。
最近はそういう教育に変わってるのかな?
教育論に関しては守備範囲外なので、ひとまず置いておきます。
それとは別に、人間には感情というものがありますから、それもアウトプットの自主選択を歪めてしまう原因になります。
「ついカッなって」とか。
そういうものを否定するわけではありませんが、結果として「自分の不利益になる結果」をもたらしてしまうのであれば、できればそうならないようにしたいものだと思います。
そういう時は、インプットとアウトプットの間に、すこし時間を挟めば解決することも多いでしょう。
人間の脳は非常によく出来ており、じっくり思考する回路と、即座に反応する回路が混在しています。
よく「脊髄反射」なんてことを言いますが、先程書いた「カッとなって」など、その代表的なアウトプットですよね。
だから、良いことも悪いことも(良いインプットも悪いインプットも)反応を返す前に、少し時間を置くようにすると良いのだと思います。
時間を置くことによって、即座に反応する回路から、思考する回路に移行することができるようになります。
それでも頭に入れておくことで変わることもある
こういう話をすると、なんとなく分かった気がすることがあります。
でも「言うは易し行うは難し」です。
そう簡単に人は変われませんし、失敗して落ち込むこともあるかもしれません。
ただ「人間とはそういうものだ」と割り切ることも必要です。
その上で「アウトプットは自分に選択権がある」ということを意識しているだけでも良いと思います。
矛盾するように聞こえるかもしれませんが、人は簡単には変われない代わりに成長はできるものです。
成長とは継続の先にあるものです。
できなくても継続している内に、いつの間にかできるようになったりします。
私が中学生の時、サッカー部に入ったのですが、そこでは入部テストというのがあったんですよ。
それはリフティングが100回出来ること、というのが条件でした。
これが出来ないと、入部すら認めてもらえません。
そこで、グラウンドの片隅でリフティングをしてみたのですけど、小学生の時はサッカーしていませんでしたので、当然3回ほどしか出来ません。
顧問の先生は、全く教えてくれませんでした。
元々サッカーをやっていた人たちは、あっという間にクリアして練習に加わっていったんですけど、私を含めて5人ほどは毎日ずっとリフティングばかりしていました。
半月くらいだったかと思うんですけど、気がついたら50回くらいは楽勝できるようになったんですよね。
そこからは結構早くて、あっという間に100回クリアして入部が認められました。
これは私だけではなく、残っていた5人も、ほぼ同じ時期に出来るようになっていました。
これは頭ではなく体を使った経験ですが、人っていうのは繰り返すことで出来るようになるものだと思います。
言い換えれば、出来るようになるには繰り返すしかないと思います。
まとめ
今日はインプットに対するアウトプットの話をさせて頂きました。
実は今日の話自体も、同じことが言えます。
ここに書かれた話を、自分の中でしっかり考えて「ちょっと違うな」と結論が出たのなら、それはそれで良いことだと思います。
一番良くないのは「なんとなく分かった気になった」ということです。
これだとただの時間の浪費にしかなりません。
とは言え、小説を書く方にとっては、案外難しいことではないかもしれませんね。
小説を書く際には、色々なもの(インプット)がベースとなって、それを基にして創っていく(アウトプット)わけですから、そこには必ず作家の意思が入り込みます。
それと同じことですからね。
今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
それではこの辺で。おやすみなさい。



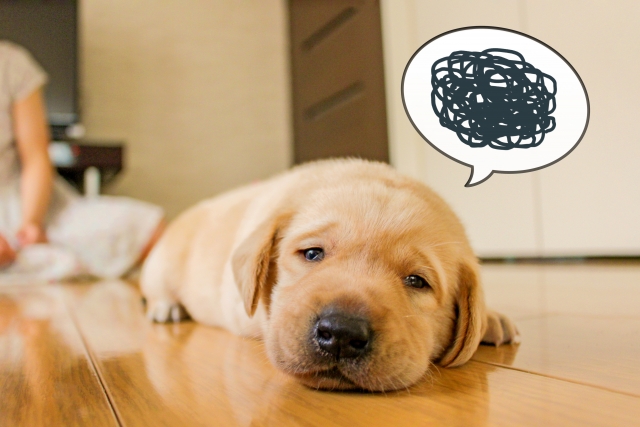










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません