小説家という職業【森博嗣|集英社新書】
こんばんは、しろもじです。
読んだ本を紹介する「読んでレビュー」。
今回は森博嗣著『小説家という職業』です。
森博嗣氏の小説はほとんど読んだことがない
森博嗣氏と言えば『全てがFになる』を始め、多くの推理小説で有名ですよね。
でも、私は森博嗣氏の小説を読んだのって『φは壊れたね』しかないんですよね。
1冊で止めたのは、この本を読んだ後小説を書いたら、自分の小説がスラスラ書けなくなったからです。
森見登美彦氏のような、独特の文体というわけでもないんです。どちらかと言うと、さっぱりとして事実を淡々と書いているような感じ。
それなのに、自分の書いた文章が、なんだか引っ張られるようになっていっている気がして、どうしてもタイプするスピードが落ちる、というかまともに書けなくなってしまいました(今は幸い戻っています)。
ま、これは人に依る部分が大きいと思いますので、一概には言えないと思いますけどね。
一方でエッセイ系は、本書から入って数冊を一気に読破しました。
本書以外で一番面白かったのは『やりがいのある仕事という幻想』。
当時は、仕事で随分悩んでいた時期でもあり(いや、今でも悩み多きなのは変わりませんが)、なだか救われた気持ちになった一冊です。
論理的な考えで、非論理的に芸術を描く
この本で非常に面白いな、と思ったのが「論理性と非論理性」です。
森氏は小説に対して非常に論理的に考えているのが、本書を読んでいると分かります。
〆切に対する考え方とか、出版後の展開のこととか、非常に理詰めで物事を考えて実行されているということが書かれています。
一方で、小説自体に関しては、後の引用にあるように「確固たる方法はない」と断言しています。
プロットもきっちりとは作らず、いきなり書くということが記されています。
いいアイディアのメモもとらないのだそう。
つまり、小説を書くこと自体は論理的に行っているわけではないということです。
これが非常に面白いと思いました。
ハリウッド系の脚本術などの本を読むと「◯%からはミッドポイントだ」とか書かれていて、それはそれで「創作のルール」という考え方で間違ってはいません。
一度は目を通しておいても損はないでしょう。
しかし、小説は生き物です。
書いている途中で、思わぬ方向へ舵が切られたり、驚くような台詞が出てくることもあります。
骨子としてのプロットは、最低限頭の中にないと書けないというのはあると思います。
でも、プロットをギチギチに決めて書いた小説って(少なくとも当人にとっては)面白くないんですよね。
これを読めば、プロの小説家に近づけるのか?
タイトルが『小説家という職業』ということで、手に取る人は「森氏のファン」か「小説家を志す」人になるのだと思われます。
そのうち後者にとって、本書を読むことで何が得られるのか?
当然「これを読んだからと言って、プロの小説家になれるわけでも、近づけるわけでもない」ということは分かりますよね。
しかし、私は本書から「投稿アマチュア作家」として「小説関連サイトの運営者」として、他のどの書籍、ウェブサイトよりも影響を受けています。
一部を本書の前書きから引用します。
もし、こうすれば良い小説(あるいは文章)が書ける、という確固たる方法が存在するのならば、それはいつの日にかコンピュータにプログラムされ、ワープロが備える機能の一つになるだろう。少なくとも文体に関しては確実にそうなるはずだ。
(中略)
大事なことは、「こうすれば」という具体的なノウハウの数々ではなく、ただ「自分はこれを仕事にする」という「姿勢」である。その一点さえ揺るがなければなんとかなる、と僕は思っている。
『小説家という職業』森博嗣著 より一部引用
このウェブサイトを開いて、やがて決まったコンセプト「小説を書いている人を応援するサイト」を実現するために何が必要だろうか? と考えた時「まずは、文法とか作法とか、そういうのは要るかな?」と思いました。
妥当と言えば妥当です。
私自身何度かそういう系統の本を読んだことはありましたが、専門家というわけでもありません。
だから「もう一度勉強しなくちゃな〜」と考えながら、自分の小説を書いていたりしたんです。
ちょうどカクヨム1作目の『Replace』を投稿し終えた辺り。
「将来、小説もAIが書いちゃう時代になっちゃうんだろうなぁ」と思ったんですよね。
ちょうど、その前後辺りでそんなニュースも流れていましたし。
だから「小説の文法とかの解説って、もう要らないんじゃないか」と思い始めました。
「『!』の後ろには空白を開ける」だとか「段落の始めは、1文字下げる」だとか、小説を書く上で当たり前と言われていることすら、不必要なんじゃないかと。
いずれのものも、誰かがどこかで決めたものであり、その前はそうでなかっただろうし、今後変わっていくこともある。
そういうものを記事にして有益なんだろうか?
なんて、疑問を感じていたんですよね。
そんな時に読んだのが、本書でした。
大いに共感し、それ以降「小説執筆の文法的なノウハウは記事にしないようにしよう」と心に決めました。
ただ、線引は難しいと言えば難しく、全くその部分に触れないというのもどうかと思い、一部ではギリギリ触れている記事もあります。
しかし、できるだけ「こうしなきゃ駄目」ということは書かないようにしています。
本書のことに、話を戻しましょう。
つまり、本書は「小説を書くためのノウハウ本」ではないということです。
もっと言えば「ほとんど参考にはならない」というのが、読んで思った本音でもあります。
参考にならないとは「小説の書き方を学べるものではない」という部分と「森氏の考え方に全て合わせられるわけがない」ということです。
森氏の他のエッセイを読んでもそう思うのですが、書いていることは間違っていないけど、あまりにも独特すぎて、一般人には真似出来ない部分があります。
でも、真似しなくても良いとも思います。
人はそれぞれ違うのですから。
大切なのは「そういう考え方もあるんだ」と知ることです。
新しい考え方に触れたからと言って、それをコピーする必要はないですよね。
「はえー」って思っておくくらいで良いんだと思います(笑)。
その中で、一部でも参考になったり、自分の自身になれる部分があればいいですよね。
私の場合は、それが上記の部分と、もうひとつありました。
印象に残った部分
最後に、一番印象に残った一文を紹介しておきます。
とにかく、書くこと。これに尽きる。
『小説家という職業』森博嗣著 より一部引用
本ブログでも、何度か書きましたが、本当にこれは大切だと思います。
(多少論調は違いますが、上の記事で触れています)
小説にもブログにも当てはまる、それ以外のことでも同じことが言えるのではないでしょうか。
今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
ブログの最新記事はTwitterにて配信していますので、是非フォローを!
それでは、また。






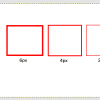




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません