音楽配信サービスのファミリー会員にみる、プラットフォーマーのしたたかな戦略
TEXT FIELD愛好者の方でしたらご存知かと思いますが、うちには現行(第3世代)と先代のEcho dotがありまして、先日ですね「古い方のdotは実家に置こうかな?」と思ったんですよ。
主目的は「呼びかけ」などの機能が使えたら便利だなぁってことだったんですが、そこで更に「どうせだったらファミリープランにして両親にも音楽を聴いてもらえればいいんじゃないか」とも思ったんです。
で、料金の一覧を見て「6人も使えるファミリープランって随分お得だよね」ってボケッと思ってたわけですが、ふと「なんでファミリープランってあるんだろう?」という疑問が湧いてきたんですよ。
色々考えている内に、ぼんやりとながら音楽配信サービスの考え方が分かってきたので、今回はそれを共有したいと思います。
これを読んでも「だからなに?」としかならないので、あくまでも読み物として楽しんでいただければと思います(あくまでも推測ですので)。
音楽配信プラットフォーマー各社の料金を再確認
まずは主要な音楽配信プラットフォーマーの料金を確認してみましょう。
| 個人会員 (月額/年額) | ファミリー会員 (月額/年額) | ファミリー 会員数 | 個人月あたり (月額/年額) | ファミリー月1人あたり (月額/年額) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Prime Music | 500/4,900 | 500/4,900 | -(※1) | 500/408 | 500/408 |
| Amazon Music Unlimited | 980/12,700 (7,800)(※2) | 1,480/14,800 | 6 | 980/1,058 (650) | 247/205 |
| Google Play Music | 980/- | 1,480/- | 6 | 980/- | 247/- |
| Apple Music | 980/9,800 | 1,480/- | 6 | 980/- | 247/- |
| Spotify | 980/- | 1,480/- | 6 | 980/- | 247/- |
| Line Music | 960/9,600 | 1,400/14,000 | 6 | 960/800 | 233/194 |
※単位は円
※1)Amazonプライムのファミリー会員にはMusicは含まれていないため、別途入会が必要
※2)Amazon Music Unlimitedはプライム会員の特典(価格低減・年払い可)があるため総額を記載。カッコ内はプライム会員費を除いた額
少し雑然とした表になってしまいました。
「個人会員」とは、ひとりで入るプランです。
「ファミリー会員」「ファミリー会員数」は、それぞれ金額とファミリー会員に登録できる人数が記載されています。まぁ6人でどれも一緒なのですが。
「個人月あたり」には個人会員の金額を12ヶ月で割ったものが入っています。月額払いであれば、同じ数字になります。
「ファミリー月1人あたり」には、ファミリー会員費を12ヶ月で割って、更に6人で割っています。
各社とも個人であれば「月額980円」くらいが標準ですね。
ファミリーであれば「月額1,480円」くらいが相場のようです。それを更に1人あたりに割ると(6で割ると)200円〜250円あたりになるのが分かると思います。

つまり個人=980円/月、ファミリー200〜250円/月となるわけで、ファミリー会員にすることでひとりあたりの金額が約1/4から1/5に減額されるわけですね。
もちろん6人以下の場合はそれぞれ計算が変わってくるのですが、話がややこしくなるので今回は最大の6人として進めていきます。
なぜこんなにも安いのか?
では、なんでこんなにも安く提供できるのか?
もちろんプラットフォーマーとしては「よりたくさんの会員数を獲得した方が音楽レーベルとの立場上有利になる」というのもあると思いますが、何より「個人よりファミリーの方が収入的にも上がるから」というのはあると思います。
これは古くから使われている手で、ファストフード店のセットなんかが有名ですよね。
| 原価 | 売価 | 利益 | 利益率 | |
| ハンバーガー | 210円 | 300円 | 90円 | 30% |
| ポテト | 60円 | 250円 | 190円 | 76% |
| ドリンク | 20円 | 180円 | 160円 | 89% |
| セット | 290円 | 650円 (80円オフ) | 360円 | 55% |
値引きしても、主要な商品(ハンバーガー)だけを売るより利益率が上がるというわけです(30%→55%)
(価格、利益などはあくまでも仮定の話です!)
音楽配信の場合は「原価」はレーベルなどによって変動はあっても、仕入れという概念はないため、上の例以上に利益率は高く見積もることができると思われます。
どういう契約なのかは不明ですがKDPのような形式であれば、プラットフォーマーは契約数を増やせば増やすほど利益が上がるということになります。
しかしながら「それならここまでの値引きは必要ないのではないか?」という疑問も残ります。
1,000円取れるものを200円にする理由はなんでしょうか?
そこで話は冒頭に戻るのですが、私が家族のためにファミリー会員を契約してみたときのことを考えてみました。
ファミリー会員は「契約が切りにくい」
例えば家族にEchoを手渡し、ファミリー会員で音楽を聴いてもらったとしましょう。
もし「やっぱりGoogleの方がいいな」と思っても、個人であれば簡単に乗り換えることができますが、ファミリー会員となると途端に敷居が高くなります。
理由はふたつあって、1つ目が「家族の同意が必要となること」です。
Echoに慣れ、Alexaに慣れてくると、他のものへの移行が面倒になります。
これをお読みになっているような「ある程度デジタルデバイスに対するリテラシーが高い方」であればGoogleだろうがAppleだろうが乗り換えるのは簡単です。
「Alexa」が「OK、Google」になるか「Hey,Siri!」に変わるか程度で、多少の音声コマンドの違いなどすぐに慣れてしまうでしょう。
でもそういうのが苦手な方にとっては「折角覚えたのに」と不満を覚えることになるのではないでしょうか?
「いいじゃん、Alexaで! なんで変えるの!?」と怒られるかもしれません。

もうひとつの理由が「デバイスのリプレース費用」の問題です。
複数のEchoデバイスを全てGoogle Homeに買い換えるのはとても大変です。
が、もちろんこれはスマートスピーカーを使っているという前提の話です。
スマホだけであれば、これは問題になりません。
だからこそ、AmazonはEchoを安売りしてでも普及させようとしているのではないでしょうか?
Echo SpotやEcho Showなどのように「通話ができるデバイス」という売り方も「社会人になった子供が実家の親とのコミュニケーションを取るツールとして」という建前でEchoデバイスを普及させ、冒頭での私のように「ついでに音楽も聴いてもらおう」という方向に持っていきたいのかもしれません。
それは悪なのか?
では、それを「したたかで強欲的だ」と言えるのでしょうか?
あくまでも個人的な意見ですが、私はそうは思いません。
月額980円でこれだけの音楽が聴き放題になり、音声で操作するスマートスピーカーでさえ4,000円弱から買えるようになったのは、間違いなくプラットフォーマーのお陰でしょう。
これがなければ私たちは未だにCDショップに通いCDを買うか、レンタルショップに行き返却するという手間をしなければなりませんでした。
そういう利便性を考えると、プラットフォーマーの行ってきたことは、一概に責められるものではないと思うわけです。
またこれらの事業がGAFAと呼ばれるようなアメリカの企業に独占されていることを危惧される方もいらっしゃいます。
海外のプラットフォーマーに全てを握られると、いいようにやられてしまう、と。
ですが、取引先に行った公取委のアンケート結果では「楽天」が最も一方的に規約を変えている企業であるという結果が出ています。
※PDFファイルで開きます。
なかなか興味深いものです。
またデジタルプラットフォーマーだけではなく、他の多くのビジネスでも「元請けは下請けに強い」「企業は消費者の同意なしに規約の変更ができる」などは見受けられます。
この点だけを取って「Amazonは悪い」「Googleはとんでもない」と指摘するのはアンフェアというものではないでしょうか。
どうしてもアメリカの企業が嫌だったら、日本企業が同様のサービスを展開していれば良かったわけですよ。
Googleを作ってiPhoneを製造してAmazonを立ち上げて、スマートスピーカーを普及させればよかっただけです。
SONYなんかは十分それができる企業だったと思うんですけどね。
iPhoneが日本に来た頃、日本の携帯は「ワンセグ!ワンセグ!」ってやってましたから。
少し話が逸れてきていますのでこの辺りにしておきますが、要は「便利なものに消費者はお金を払うので仕方がない」ということと「日本はあのとき頑張るべきだった」と残念に思うことですね。非難じゃなく自戒も込めて、です。
【余談】デジタル時代の創作者
ミュージシャンの立場になればCDが売れてた時代の方がよかったのは間違いないところでしょう。
これは小説にも言えることかもしれませんが、クリス・アンダーソンの言う通り「デジタルデータは限りなく無料に近づいていく」のは止めることができない事実だと思います。
ただ逆に言えば「デジタルでない物質的なものは、それの対象外になる可能性がある」とも言えます。
つまりミュージシャンにとってのCD、小説家にとっての書籍は今後も価格を崩すことなく成立していける要素はあるということです。
それには「デジタルとの差別化」は必須となり、言い換えれば「付加価値をつけること」が必要でしょう。
例えばCDならばアーティストのフォトブックが付くとか、握手券……はもうあるのか(笑)。
小説でも同じだと思われます(先日の記事で少し触れました)。
いずれにしても「デジタルプラットフォームで格安にて普及させ、ファンの方に物質的なものを買ってもらう」という流れになっていくのではないでしょうか。
って言うか、すでになっている部分も大きいと思われますが。
まとめ
なんとなく思いついたことを数日間掛けて記事にしていきましたので、やや雑然としたものになってしまったかもしれません。
また、テーマがあまりにも大きすぎるため、1記事でまとめられないものを無理やりまとめてしまい、大雑把な記事にもなっているかもしれません。
冒頭にも書きましたが「だからなに?」的な話ではありますが、プラットフォーマーという部分で考えると、昨今の小説投稿サイトの乱立にも似たような要素があるのかもしれません。
数多くの投稿サイトが立ち上がっていく中、生き残って市場を独占していくためには「小説を投稿できますよ。タダで読めますよ」という価値観だけではなく、利用者が「おぉ、すげー!」と感動したり、興奮したりするような仕組みが必要なのかもしれません。
ただ「ウチは大手だから」だけで続けていては、以前の日の丸家電メーカーの轍を踏む可能性もありますしね。
デジタルプラットフォームは抑えられても、コンテンツプラットフォーム、それも従来のものではなく新しいプラットフォームは日本から世界に羽ばたいて欲しいと思います。
なんとも他人任せな結論ですが(笑)。

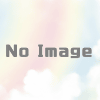

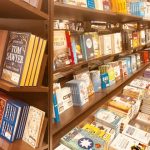









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません